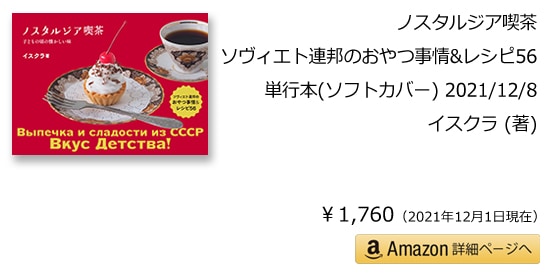<8>

ソ連赤軍がベルリン市街への砲撃を開始した4月20日は、折しもヒトラーの56歳の誕生日であった。
魔術的ともいえるカリスマ性でドイツ全土を熱狂させ、周辺国も驚くような国家再興と欧州大陸侵略を実現したヒトラーだったが、帝都陥落の危機に直面している今、過去の栄光は既になく、この日の誕生祝賀会も、ベルリン中心部の地下に秘密裏に建造された“総統地下壕”の、湿った狭い一室で執り行われた。
この頃からヒトラーは、錯乱に近い状態に陥る。もはやドイツには、東西から進撃してくる敵軍を食い止ることが出来る軍事力は無かったが、ヒトラーはその事実をどうしても受け入れることが出来ず、ベルリン周辺にわずかに残った残存兵にちかい部隊に対し、到底実現しようのないベルリン救出の指令を出し、それが進捗していないとの報告を受ける度に、机を叩き、怒号を発した。
ベルリンの陥落は明らかだった。側近たちは、ヒトラーに対し、包囲の輪が完全に閉じてしまう前にベルリンから脱出し、反抗の機会を伺うべきだと進言したが、ヒトラーは断固これを拒否し、あくまでベルリンで闘うと主張して譲らなかった。ベルリンは、彼の妄想が具現化され、一時的にであれ、世界を席巻するかに見えたナチ的世界そのものだったのかもしれない。
ヒトラーの敵は、自分を否定し、排斥した世界の在り方そのものだった。その世界の在り方に“闘争”を挑み、自らの手で作り上げたナチ的世界が今、終焉を迎えようとしている。かつて自分を踏みにじったあの世界に戻って生き続けることになど、何の意味があるであろう。彼にとっての“世界の終わり”が迫りつつあったこの時、ヒトラーは、自らの人生をどのように振り返っていたのであろうか。
青年期までのヒトラーの人生に、華々しいものは何一つなかった。
ヒトラーの家系は非常に難解である。彼の父アロイスは、未婚であった女性の私生児(婚外子)として生まれ、その実父が誰であったかの記述はない。アロイスが5歳の頃、母が粉ひき職人ヨハン・ゲオルグと結婚した際、アロイスはヨハン・ゲオルグの庶子として認知され、養育のためヨハン・ゲオルグの弟で農夫であったヨハン・ポームネクの家に引き取られた。アロイスは、14歳で家を出て靴職人の徒弟となったが、その後苦学を経て税関士となり、出自のハンデを克服して上級職員にまでなった。
アロイスは多数の女性と関係を持ち、少なくとも4人の女性との間に子を設け、3度結婚している。ヒトラーは、アロイスの3番目の妻クララの子アドルフとして、この世に生を受けた。クララは、アロイスの養父であったヨハン・ポームネクの孫娘にあたり、家政婦としてアロイスの元で働いていてお手が付き、やがてヒトラーを生んだ。複雑という他ない。
なお、上述の通り、アロイスの父、すなわちヒトラーの父方の祖父が誰かは不明である。ヒトラーに、実はユダヤ人の血が入っていたという都市伝説めいた話しがあるのはこのためだが、戸籍上、妻の連れ子としてアロイスを引き取る形をとったヨハン・ゲオルグか、その弟のヨハン・ポームネクが、アロイスのそもそもの父親だったのではないかとの説もあり、ユダヤ人説はほぼ否定されている。
いずれにせよ、ヒトラーにとって、彼の家系は、他人に誇れるようなものでは全くなかった。ヒトラーは、家系について詮索されることを極度に嫌い、一族という概念を全く持たなかったという。ヒトラーは、自らの血の栄光を、直接的な先祖ではなく、ドイツ民族という、より大きな共同体に求めるしか、道がなかったのかもしれない。
アロイスは、ウイーンの北西100km辺りに位置するオーストリアのシュトローネスという村の出身であり、ヒトラーはドイツ国境に近いブラウナウという街で生まれている。従ってヒトラーは、ドイツ民族ながら、生来の国籍はオーストリア人ということになる。
ヒトラーが小学校に上がるころ、アロイスが定年して恩給生活に入ったため、一家は田舎に引っ越して農業を営むことになった。しかしアロイスは、この農場経営に失敗し、程なく一家を連れて都会に戻り、何度か転居した。アロイスは、子供の頃の不幸な境遇を自ら乗り越え高級税関士として出世を果たしたことを常々誇りとしており、その虚栄に、その後農業に失敗した苛立ちも加わってか、家庭内で暴力的に振舞った。ヒトラーには兄がいたが、父の横暴が理由で家を飛び出し、兄がいなくなった後は、アロイスの暴力の矛先はヒトラーに向かうこととなった。
ヒトラー自身、学校の規律に馴染めず問題児となっていたことも、アロイスがヒトラーを折檻する一つの理由であった。ヒトラーが中等教育に進むにあたり、本人は、大学進学に繋がるギムナジウムで学びたいと強く願っていたのに対し、アロイスは、職業訓練学校に進むことを強要し、ヒトラーはこれに激しく反発し、授業をサボタージュした。
ヒトラーは、小学校の段階で既に落ちこぼれており、実科学校への進学を求めたアロイスの意向は、実科学校を経て手に職を付けなければ後々ヒトラーが生計を立てていけなくなるという親心も多分にあってのことだったと思われるが、ヒトラーからは、父アロイスによって自分の将来が閉ざされたと見えたのかもしれない。
父アロイスは、そうした父子の確執のさなか、ヒトラーが14歳だったときに脳卒中で他界する。ヒトラーは、その後も落第や非行を繰り返し、アロイスの死から2年後、16歳だった時に実科学校を退学した。故に、彼の最終学歴は小学校である。
ヒトラーは、学校も嫌いだったが、額に汗して働くことも嫌いだった。画家になることを夢見て、父の遺産を資金としてウイーンに移り住み、美術アカデミーを受験するが不合格となった。彼の絵は、描写は丹念であったが創造性がなく、芸術性に乏しかった。ヒトラーを不合格にした美術アカデミーからは、いっそ建築家を目指してはどうかと勧められ、ヒトラー本人も、それこそ自分が目指すべきものだとの思いに至り、猛勉強した。
が、ヒトラーは、程なく、それもむなしい夢だったことを思い知らされる。建築家になるためには建築アカデミーで学ばねばならず、そのためには実科学校の卒業資格が必要だった。彼は、実科学校に残り、そこを卒業すべきだった。青年ヒトラーの人生は、既に夢から遠く離れたものになっていた。
さらなる不幸がヒトラーを襲う。ヒトラーの母クララが乳癌を患い世を去った。クララは、問題の絶えないヒトラーの行動に心を痛めながらも、この一人息子を溺愛した。ヒトラーもクララを愛し、母の臨終前の数か月間、ひと時も傍らを離れなかったという。「クララが死んだ時のヒトラーほど打ちひしがれた人間を、私は未だかつて見たことがない。」とクララの死を看取った医師が後に語っている。
母が死んだ後、ヒトラーは再びウイーンに戻り、無為に日々を過ごした。何もかもが許せなかった。
当時のオーストリアは、ハプスブルグ家が統治するオーストリア=ハンガリー帝国という多民族国家であり、その首都ウイーンは、帝国版図であるオーストリア、ハンガリー、チェコ、そしてバルカン諸国の民族が混交して住む国際都市となっており、文化の爛熟期にあった。所謂“世紀末ウイーン”である。しかし、ロマン主義の画家を志向したヒトラーにとって、退廃的ともいえる当時のウイーンの芸術は、吐き気を催すほど忌まわしきものだった。
ヒトラーにとって、さらに許せなかったのはユダヤ人の存在であった。時の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は、文化芸術を熱心に庇護したとともに、宗教的にも寛容であったために、当時の東欧で猛威を振るっていた“ポログム”から逃れてきたユダヤ人たちが大量にウイーンに移り住み、金融を中心とする実業の世界のみならず、文化芸術の分野でも大いに活躍していた。音楽家のマーラー、作家のカフカ、心理学者のジークムント・フロイト、アルフレッド・アードラーはいずれもこの時期のウイーンで名声を得ている。
そうしたユダヤ人の活躍に脅威を感じていたのはヒトラーだけではなかったようで、当時のウイーンは、反ユダヤ主義運動の中心となり、同時に、ユダヤ人たちが約束の地エルサレムへの回帰、イスラエルの再建国を求めて起こしたシオニズム運動の中心ともなった。
当時のウイーンで展開されたそうした混沌とした世界の在り方を、ヒトラーは心の底から憎んでいた。自分を取り巻く世界の在り方は根本的に間違っていて、そのせいで自分は、このように不当に貶められた状態におかれたのだ。それは、自らの将来を潰した存在である父アロイスの像とも重なっていたのかもしれない。アロイスは生粋のハプスブルグ王朝支持者であった。
ヒトラーは、そのウイーンで20歳を迎え、兵役に就くべき年齢となっていたが、そんなハプスブルグ帝国のために銃を取って戦場に行くなど到底受け入れられるわけもなく、兵役忌避を目的としてか、敢えて浮浪者収容所に入り、そこで生活したりしていたが、やがてウイーンから姿をくらませた。
ヒトラーが移住した先は、ドイツ帝国の南部、バイエルン州の都ミュンヘンである。ドイツ帝国とオーストリア帝国は、もともと神聖ローマ帝国という一つの集合体を形成していたが、中世以来の名門王朝であるハプスブルグ・オーストリアと、北部ドイツから起こった新興勢力のプロイセンが対立して分裂した。その結果として、プロイセンが神聖ローマ帝国下の諸侯を従えて建国したのがドイツ帝国であり、そこから排除されたハプスブルグ・オーストリアが隣国ハンガリーと合併して出来たのが、オーストリア=ハンガリー帝国であった。必然的に、両者は気質の全く異なる国であった。
ヒトラーは、ドイツ帝国の国体、すなわち、ドイツ民族としての血に栄光を感じ、武をもって世界に覇を唱えようとする在り方に、自分が目指したかった理想を重ね、失われていた自分の未来を見出そうとしたのかもしれない。だとすれば、彼の判断は正しかったといえるだろう。ヒトラーは、24歳になった年にミュンヘンに移住し、そこから、独裁者への階段を徐々に上っていくことになるのだから。
<9>

ヒトラーは、24歳になってすぐの1913年5月にミュンヘンに移り住んだ。しかし、母国オーストリアで兵役逃れの罪を犯した彼は、故郷リンツの警察から委託を受けたミュンヘン警察によって、程なく拘束されている。ヒトラーは、オーストリアに戻って兵役検査を受けることを強いられるが、彼にとって幸運なことに、栄養失調で兵役不適格との判定を受けた。
ヒトラーがオーストリア兵としての兵役不適格通知を受けたのは1914年1月だが、その年の8月1日に第一次世界大戦が勃発すると、なんとヒトラーは、この戦争に、オーストリア国籍のままドイツ帝国軍(その一部であるバイエルン陸軍)に志願し、同軍の義勇兵となった。
ヒトラーは、幼いころからドイツ国境近くで育ち、ドイツ人を間近で見てきた。ヒトラーにとってのドイツは、誇り高き単民族主義を掲げ、新興で勢いのある頼もしき存在であり、既に老い、多民族国家として分裂の危機にあった母国オーストリアとコントラストを成す、“隣の芝生”的な憧れの存在であった。
バイエルン第16予備歩兵連隊に従軍したヒトラーは、伝令兵となった。職位は上等兵である。ヒトラーは、連隊の中においても、地味で目立たず、控えめで卑屈。しかし切れると面倒な、“変わった奴”的な存在だった。仲間の兵士は、恋人や家族からの手紙を心待ちにしたが、ヒトラーの手元には一通の手紙も来なかった。彼はどこまでも孤独であった。
ヒトラーは、部隊に迷い込んできた子犬を可愛がり、名前を付け、芸を仕込んだ。ある時、部隊が戦地を変わるため移動している最中に、この子犬と、彼が大事に書き溜めてきたスケッチが行方不明になってしまい、大いに傷心したという。後の、独裁者として世に知られる彼とは、全く別の人格のような印象を受ける。
しかし、ヒトラー本人は、軍隊に自分の居場所を見出した感があり、死を顧みず、黙々と、時に大胆に、伝令兵としての職務を執行し、1914~1918年の4年の兵役の間に6つもの勲章を授与されている。なかなかの働きといってよい。
通常であれば、下士官に昇進してもよい状況であるが、ヒトラーの職位は上等兵のままだった。ヒトラーは後に、伝令兵としての職務執行こそが自分がやりたいことであり、昇進には興味がなかったからだと言っているが、当時のヒトラーには人望も統率力も、自らへの自信もなく、情緒的にも不安定で、とても人の上に立てる人物ではないと上層部から見なされていたことが真相だったようである。
開戦が5年目に入った1918年秋、ヒトラーはベルギー方面の前線でイギリス軍と対峙していた。同年10月13日未明頃、ヒトラー達の塹壕に敵軍の毒ガス弾が撃ち込まれた。使用されたのはマスタードガスで、塹壕でこの直撃を受けたヒトラーの同僚たちは失明状態に陥った。伝令兵だったヒトラーがどの程度の至近距離でマスタードを浴びたのかは定かではないが、いずれにせよヒトラーは、後方の野戦病院に搬送された。
ヒトラーが従軍した第一次世界大戦は、サラエボでのオーストリア皇太子夫妻暗殺事件をきっかけに、オーストリアがセルビアに宣戦布告したことで始まった戦争だったが、バルカンへの勢力拡大を目論むロシアがセルビアを擁護する立場でオーストリアに宣戦布告し、さらにはオーストリアの同盟国ドイツ、ロシアの同盟国フランス、イギリスの列強各国が次々と参戦する形で、戦線は欧州全土へと拡大した。さらには、トルコ、アメリカ、日本等も参戦し、この戦争は、人類初の世界大戦へと発展したのである。
オーストリア、ドイツ、ロシアを中心とする同盟国と、フランス、イギリス、イタリア等からなる連合国の2陣営に分かれて戦うことになった第一次世界大戦だが、そもそも、列強国間でお互いの領土を直接的に侵攻されたわけでもないまま宣戦を布告し合ったこの戦争は、何がどうなれば事の白黒が付くのかが不明確だった。また、各国の実力も拮抗していたため、この人類初の世界大戦は未曽有の消耗戦となり、前線の兵士と後方の国民を苦しめた。
前線の兵士の苦しみをより深くしたのが、各種兵器の進化である。それまでの戦争では、敵味方の両軍が、開けた土地での開戦をもって、歩兵の銃剣突撃と砲兵の相互射撃で激突し、短期間で決着がついていた。
機関銃の普及がこの戦い方を一変させた。敵陣に銃剣突撃を試みても、兵隊達は機関銃の掃射によってハチの巣にされ、空しくその地に倒れるだけである。その結果として、敵味方の両軍は、最前線に塹壕を掘り、そこに機関銃を据え、お互い睨み合ったまま動けない状態となり、戦線が膠着した。
塹壕戦を戦う兵士の境遇は過酷を極めた。雨ざらしの塹壕に何日も留まることを強いられ、兵士たちは、容赦なく照り返す日差しの中で乾き、またある時は降り続く雨に打たれ、寒さに震えた。戦闘服は何日も変えることが出来ず、シラミが沸いた。塹壕には何十匹ものネズミもはびこり、戦闘の緊張の中、束の間の仮眠を貪る兵士たちの顔を齧った。塹壕では病気も蔓延し、赤痢になった兵士たちは、塹壕の中に自らの血便をぶちまけた。
しかしそれ以上に恐ろしいのは、自軍の上官による突撃命令だった。一度その指令が出れば、有無を言わさず塹壕から這い上がって、敵陣地に向かって突撃しなければならない。大半の兵士は、機関銃の餌食となり、屍になってその場に斃れた。突撃命令に従わなくてもまた、待っているのは軍令違反による死罪であった。最前列の塹壕には、複数の部隊が交代で配備されたが、兵士たちは、自分たちが最前線にいるときに突撃命令が出ないことを切に願いながら、戦場での日々を過ごした。
突撃がなくても、敵軍の砲弾が塹壕に命中し、分隊が諸共に吹き飛ぶことも日常茶飯事だった。さらに、大戦の中盤からは毒ガスが登場し、兵士たちの悲惨さをさらに深刻なものとした。毒ガスは、兵士たちの目を潰し、皮膚を爛れさせ、実弾に被弾する以上の苦しみを彼らに与えた。
第一次世界大戦の前線兵士達が置かれていたのは、そうした剥き身の痛み、想像を絶する精神的苦痛が、果てしなく続く生き地獄の世界であった。一方で、名門家の人々で占められる軍と国家の上層部の人々は、そうした苦しみとは全く別の世界に生きていて、それでもなお、庶民と前線の兵士に、まるでそれが当たり前のことであるかのように苦しみ続けることを強いた。各国の前線兵士は、やがて、敵軍より自国の為政者と特権階級を憎むようになった。その不満は後方で困窮と飢餓を強いられている庶民も同じであった。
各国におけるそうした国民と兵士の不満はやがて頂点に達し、ロシアではレーニンによる共産革命が勃発してロマノフ朝を倒し、新政権のソ連は大戦からの撤退を決めた。オーストリアも体制が崩壊して戦線を離脱し、同盟国で残るのはドイツ1国となった。
ヒトラーが前線で負傷し、野戦病院に送りこまれた1918年秋は、そのような事情でヨーロッパ社会が激変し、大戦が終焉に向かいつつある、正にそんな時代だった。
ヒトラーは“祖国”ドイツの在り方に全面的に賛同し、末端ではあったが、戦場でその国威の執行者として行動することに、それまでに経験したことのない手応えと満足を感じていた。第一次世界大戦は、各国勢力が一進一退を繰り返す泥沼の戦況だったが、武に長じたドイツは、その中の有力国であり、前線のヒトラーは、”祖国”の勝利を信じて疑わなかった。
そんなヒトラーの元に、衝撃の事実が知らされることとなる。ヒトラーが野戦病院に入院してひと月が経とうとしてた11月10日、一人の牧師が野戦病院を訪れて、ある事実を患者たちに伝えた。
ドイツ帝国が、この戦争に敗北したというのである。11月に入ってから、ドイツの命運は急転していた。11月3日、キール軍港における水平の反乱をきっかけとして、ドイツ全土で、兵士や国民が蜂起した。暴動は共産革命の色を帯び、ドイツ革命となって帝政を崩壊せしめ、10日には革命政府が設立され、皇帝ヴィルヘルム2世はオランダに亡命した。全ドイツ国民と前線の兵士達のよって立つ基盤であったはずの帝国が崩壊したのである。
ドイツ帝国は、確かに不利な戦況にはおかれていたが、全面的な敗北というわけでもなく、ヴィルヘルム2世と帝国軍部は、夏過ぎから停戦の可能性を模索していた。その土台が革命によって足元から崩され、新たに成立した革命政権は、なすすべもなく、ドイツにとってあまりにも屈辱的な講和条件を受け入れるに至るのである。
11月10日のこの時点では、牧師が伝えた事実は、帝政が崩壊して共和制に移行したこと、それは同時に敗戦を意味するということであったが、同時に牧師は、ドイツはこの先、戦勝国の慈悲と寛大なる措置にすがり、その境遇に耐え忍ばなければならないとも語った。
ここに至り、ヒトラーの失望と怒りは頂点に達する。こんなことのために・・・彼は、絶望の淵に追い詰められ、心の中で絶叫した。自らが経験した前線でのあの過酷な日々。死んでいった仲間の兵士達。銃後の母と家族の悲しみ。その全ての犠牲の報いが、まさかこのような屈辱的な結果であろうとは。
それは、“祖国”の敗戦のみならず、それまでの人生で、何一つうまくいかなかったヒトラーが漸く見出した明るい未来が、足元から崩れて消え去ることも意味していた。
ヒトラーは、それ以上その場にいることが出来なくなった。彼の頭は怒りで炎のように熱く燃え、その場に立っていられなくなってベッドに倒れ込んだ。
何もかもに失望したヒトラーの目は、光を失って、何も見えなくなった。
ヒトラーの失明は、前線で毒ガスを浴びたためだと本人は証言しているが、正しくは、敗戦の報を聞き、極度のパニック状態に陥ったことによるヒステリー性の失明だったのではないかとの説がある。そのどちらが真実だったのかは、今となってはわからない。何故なら、ヒトラー本人が、政権奪取後に、この野戦病院での自分の治療記録を全て押収し葬り去っているからである。
いずれにせよ、この野戦病院で敗戦の報を聞いたヒトラーは、失明によって漆黒の闇に陥れられた。しかしこの経験が、ヒトラーの人生の一大転機となるのである。その闇から戻ってきた頃から、彼は、それまでとは全くの別の人物、独裁者ヒトラーになっていったのである。
<10>

ヒトラーは、何日かの間、暗く深い心の闇を彷徨った後、現実世界に戻ってきた。視力が劇的に回復したのである。視力の回復と同時に、ヒトラーは、それまでとは全く別人のような人格になっていた。周りに対する不平不満を山ほど抱えながらも、結局何事も成しえない日陰者だった男が、鋼鉄のような意志を持って、ある一点を目指し突き進み、魔術のような力で周りを巻き込んでいく男に生まれ変わったのである。
第一次世界大戦は終わった。足掛け5年に及んだこの戦争は、欧州を中心に民間人600万人超を含む1600万人以上もの人命を奪い、交戦各国の国力を著しく疲弊させ、ロシア、オーストリア、ドイツ、トルコの4つもの帝国を崩壊させるというという凄まじい惨禍をもたらした。戦勝国となったイギリス、フランスも、世界の覇権国家としての権勢を大きく後退させ、国家の財政は危機に瀕した。勝者無き戦争だったといって良い。
ドイツは、この大戦中、軍事的には決して劣性ではなかったが、戦争の後半になると、経済封鎖等により国力の疲弊が色濃くなっていった。少しでも優位な状況で停戦を模索したいドイツは、1917年末にレーニンによる共産革命でソ連政権となったロシアとまず講和し、1918年春には対英仏の西部戦線に戦力を集中して一大攻勢に打って出た。ドイツは、緒戦では善戦するが、やがて兵站が追い付かなくなり戦線が膠着。さらにはアメリカが英仏側に参戦したことで一気に戦況を悪化させてしまった。
ドイツは、参謀本部のルーデンドルフが内政でも実権を掌握し、国家総動員による総力戦でこの戦争を戦ってきたが、国力の疲弊、国民の不満ともに限界に達しつつあったこともあり、1918年の夏から、ベルギーのスパにあるドイツ大本営を窓口としてアメリカとの停戦交渉を開始した。が、アメリカ側が、ドイツが帝政から議会制民主主義に移行することと、軍事力の徹底的な削減を要求したため、ルーデンドルフはこれに拒絶反応を示し、交渉が迷走した。
その最中の11月3日にドイツ北部のキール軍港で水兵の反乱が起こって、これが瞬く間にドイツ全土に飛び火し、革命となってドイツ帝国が崩壊してしまったのである。ドイツは、講和交渉上圧倒的に不利になった。講和交渉には、条件が折り合わなければ戦争を続行するというカードが必須だが、それを失ってしまったのである。
それでも、この講和交渉がドイツにとってそんなに酷いことにはならないだろうとの期待もあった。時の米大統領ウィルソンは、民族自決と人道を重んじ、戦勝国による過度な賠償請求を否定し、公平な講和を行うとの考えを掲げて仲介役を買って出ており、ドイツ政府もその前提で講和交渉を行っていたからである。
一方、非常に強硬だったのはフランスである。フランスは、1870~71年の普仏戦争でドイツ(プロシア)に敗戦してアルザス=ロレーヌを奪われ、第一次世界大戦でも、ドイツ軍にフランスの主要な工業地帯である東北部へと深く侵攻されて、一時はパリも包囲の危機に晒されたため、ドイツに対する深い怨恨と、深刻な恐怖心があった。このためフランスは、ドイツが二度と戦争出来ない様に、軍事力を全てもぎ取り、経済的にも徹底的に叩きのめすことに強く拘った。
イギリスは、米仏の中間ぐらいの立ち位置にいたが、世論や議会の圧力によって講和方針が大きく振れた。アメリカ大統領ウィルソンも、彼個人が掲げていた理想は極めて崇高で、ヴェルサイユでの講和交渉のために米大統領として初めて欧州を訪れた際には“正義の人ウィルソン”として大いにもてはやされたが、実際の外交では強硬一点張りのフランスを説得しきることが出来ず、アメリカ本国議会の支持も十分に得られないまま、結局、彼の理想をドイツとの講和条件に具体的に落とし込むことは殆ど出来なかった。
講和というものは、通常、戦勝国、敗戦国の直接の対話で条件交渉が行われるものであるが、講和条件をどうするかの話し合いはドイツ抜きでなされ、ドイツは、全て決まった段階で漸く呼ばれ、一方的にそれを飲むことを強要された。
ドイツに突き付けられた講和条件の主なものは以下の通りである。講和会議はヴェルサイユ宮殿で行われたため、締結された講和条約はヴェルサイユ条約と呼ばれる。賠償金については、講和会議中に決着せず、その後連合国賠償委員会が決定したが、以下は、その賠償条項も含んでいる。
<領土関連>
・アルザス=ロレーヌ地方のフランスへの返還
・ドイツ東部バルト海地域の割譲(=“ポーランド回廊”の確保/東プロイセンの飛び地化)
・ベルギー、デンマークへ等の一部領土割譲
・全ての海外植民地の放棄(山東省、南洋諸島、サモア、ニューギニア、カメルーン、ブルンジ、ルワンダ、タンザニア、ナミビア、トーゴ)
<軍事関連>
・徴兵制の廃止、軍備の大幅制限(兵員10万人)
・飛行機、戦車、潜水艦等保有の禁止
・ライン川西岸流域(フランス近接地域)の非武装化
<経済関係>
・ザール地方炭鉱兼権のフランスへの譲渡
・船舶引き渡し、家畜引き渡し(20万頭超)、石炭をはじめとする鉱物無償納入等の現物による賠償
・賠償金1320億マルクの課金
これにより、ドイツは、海外領土の全てと、本国領土の4分の1を失った。しかし、それ以上に過酷だったのは、賠償金の重さである。これを外貨で30年に渡って払い続けるのである。1320億マルクは、当時のドイツのGDPの2.5倍、国家予算の20倍である。
我が国の2019年の名目GDPが約534兆円であるから、その2.5倍は1335兆円。実額としては想像しようもない巨額であり、国家予算の20倍という切り口で捉えたほうが、その深刻さがわかりやすいかもしれない。ただでさえ苦労して捻出する国家財政の20倍もの金額を、国外に払わなければいけないのである。ドイツの国家財政の破綻は必至である。
あまりの条件の厳しさに唖然とするほかない。勝者となった連合国は、ドイツの庶民が近代国家国民として人がましい生活をすることを認めず、また、国家としてのドイツにも、国際社会の一員とみなして対等に付き合うという尊厳を与えなかったといっても過言ではない。
かつてローマ帝国がカルタゴとの3度の戦争を経て勝者となった時、ローマは民族としてのカルタゴ人をほぼ根絶やしにし、その国土に塩をまいて、カルタゴという民族と国家の存在を、歴史の中から完全に消し去った。敗戦国となったドイツには、4分の3にはなってしまったが、それでも欧州の一大国の規模を持つ国土と、そして6500万の国民が残されただけ、カルタゴよりましだったと言えるだろうか。
この厳しすぎる賠償規定については、米英仏においても批判的な意見も多数出ていた。フランスの歴史家ヴァンビルは、連合国のドイツに対する扱いを「過酷な点があるにしてはあまりに手ぬるく、手ぬるい点があるにしては過酷に過ぎる」と称した。
ヴェルサイユ体制下の国家ドイツへの賠償条件の決定をもって、ドイツ国民の復讐は必定となったと言って良い。後は、誰がどのような形でそれを実現するかだけの問題である。
<11>

後にドイツの復讐を託された男がヒトラーである。失明から回復したヒトラーは、部隊の本拠地であったミュンヘンに戻った。
第一次世界大戦の終結と相前後して、皇帝ヴィルヘルム2世はオランダに亡命し、共和制のドイツが誕生した。共和制憲法が制定された都市ワイマール(ヴァイマル)の名をとって、ワイマール共和国とも呼ばれるが、正式な国号はドイツ国であり、首都は帝政時代に続きベルリンに置かれた。
大戦後のドイツは常に動乱の状況にあった。ワイマール政府の力は弱く、生活が立ち行かなくなった人々の心はすさみ、極左共産勢力と、復員兵を中心とする右派の義勇兵等が耐えず暴動を起こし、暴徒と化した政治勢力同士が街中で殴り合い、時には銃火器まで持ち出して流血沙汰になることがドイツの常態になった。
ヒトラーが復員したころのバイエルン(ミュンヘンはその中心都市)は、もともとドイツ帝国内の地域王国だったが、中央政府と地域王政に反抗する革命が起こり、レーテと呼ばれる共産勢力の支配下にあった。しかし、レーテ政権は統治能力に乏しく、程なく、ベルリンから進軍してきたワイマール中央政府によって打倒された。
ヒトラーは、そうした動乱の中、一旦はレーテの評議員になったりもしたが、ワイマール中央政府によってレーテが倒されると、中央政府の“目明し”的に、ミュンヘンの政治活動家たちに共産主義的傾向があるか否かを調査する職務に従事し、その実力を評価されるようになった。
ある時ヒトラーは、ミュンヘンの場末のビアホールで集会を開こうとしている政治集団の調査を上官から命令された。ドイツ労働者党/DAPと名乗るその政党は、名前だけは立派だったが、その集会は、20人ばかり人々が集っているだけの、あまりぱっとしないものだった。しかし、この集会で、ヒトラーがとあるテーマについて党員の一人と激論となった光景を見て、同席した人々はヒトラーの弁舌の鋭さに驚き、心酔した。ヒトラーは、初登場ながら脚光を浴びる存在となったのである。
弁舌。それは、失明から回復したヒトラーに備わった不思議な能力であった。ヒトラー自身、政治調査員としての職務に従事する中でこの能力に気づき始めていた。DAPの創始者ドレクスラーは、ヒトラーをスカウトし、ヒトラーもこれに応じDAPに入党した。
ヒトラーはまた、軍の諜報員として活動していた時代に、復員兵に反ボルシェビキズム(反共産主義)的思想を植え付ける指導員としての教育を受けていたため、このナレッジも、教宣活動の素人集団だったDAPの役に立ったようである。正規の党員となったヒトラーは、その弁舌と教宣能力で党の支持者を増やして党の看板のような存在となり、党内での実力を徐々に掌握していく。
ヒトラーがDAP集会に潜伏する指令を受けたそもそもの理由は、DAPに共産思想がないかを調べるためであったが、実際のDAPは強烈な反共産、反ユダヤ主義を掲げる極右政党であった。ドイツ労働者党という名称がこのあたりの紛らわしさを生んでいたこともあり、ヒトラーが入隊して暫くして、DAPは、その名称をドイツ国家社会主義労働者党/NSDAPに変更した。略称は、国家社会主義/Nationalsozialistの一部をとって、Nazis/ナチスと称した。
一方、ドイツの情勢は、その後も右派のクーデターや左派の蜂起等で政局が一向に安定しない状態が続いていたが、1923年になるといよいよ事態が深刻になってくる。
ドイツ北西部のルール工業地帯では、労働者の蜂起が長引き、ワイマール政府はこれを鎮圧するために軍隊を派遣せざるを得なくなった。これに対しフランスは、非武装地帯に指定したルールに軍を入れるのは条約違反であると猛烈に抗議し、また、ドイツ内政の混乱で賠償金の支払いが滞っていることにも腹を立てて、ベルギーとともにルール地帯を占領してしまった。これにはワイマール政府も徹底抗議の姿勢を示し、ルールで発生したドイツ人労働者の対フランスストライキを全面的に支援するために、ストライキに参加する労働者の給与を全額保証することを約束した。
しかし、ただでさえ窮乏していたドイツの国家財政である。それが、主要産業である石炭・鉄鋼業の8割近くを担うルール工業地帯からの税収が途絶え、かつその労働者の給与を全額保証したため、財政が完全に破綻してしまった。ワイマール政府は、この休業保証のために大量の紙幣を発行した。その発行額は第一次大戦前の2000倍にまで登ったという。結果、空前のハイパーインフレーションを引き起こしてしまった。
この当時のドイツの物価上昇率は、2.5万倍、384億倍、1兆倍等、文献によって様々な記述があり、それらが何時を起点とした対比なのか、どの数値が正しいのか自分にはよくわからない。いずれにせよ、パン1つが1兆マルクとなり、100兆マルク札が発行され、人々は、日々の食材を買い求めるために手押し車に札束を山のように重ねて持っていかねばならなかったとか、モノの値段が刻々と変わるので、ビアホールで飲むときには、皆、その日飲む分のビールを最初に注文した、といったエピソードを聞くだけでも、その凄まじさが想像できる。ドイツ国民は混乱のどん底に叩き落され、民心は大いに荒廃した。
ワイマール政府は、あまりの財政負担に遂に音を上げ、ルールでの対フランスストライキとその賃金保証の停止を表明したが、それはそれで反対し激高する国民も多く、各地で暴動が頻発した。カオスという他ない。
ミュンヘンでも大きな暴動が起こったが、その首謀者はヒトラーであった。この頃には、ヒトラーは、3万人を超える党員を有するナチ党で実権を掌握し、Führer/フューラー(指導者)と呼ばれる存在となっており、彼の発案により、鉤十字/ハーケンクロイツの党旗や、ナチ式敬礼も既に採用されていた。
当時のバイエルン地方政府は強烈な反ベルリン中央政府の立場を取り緊張関係にあったが、先制攻撃としてベルリンに進軍すべきと強硬に主張するヒトラーは、バイエルン地方政府要人達が演説を行っていたビアホールを武装襲撃し、バイエルンを自らの手中に収めようとした。所謂“ミュンヘン一揆”である。しかし、ヒトラーの野望は失敗に終わり、銃撃戦でナチス党員13名が犠牲となり、ヒトラー自身も逮捕されてランツベルグの刑務所に収監された。
しかし、ドイツの窮状を憂い、中央政府に毅然と立ち向かおうとしたヒトラーの姿勢は民衆から大いに評価され、失敗に終わったこの一揆は、むしろヒトラーの名声を世に知らしめるきっかけとなった。
ヒトラーの収監中の環境も、決して悪いものではなかったという。ヒトラーは、この間に自らの半生と政治理念を口述筆記させ、後にこれを「我が闘争」として出版している。さらにヒトラーは、一旦5年の禁固刑を申し渡されたものの、1924年12月には保釈され、その数か月後に、ミュンヘン一揆以降解散させられていたナチ党を再建した。一揆の失敗に懲りたヒトラーは、以後、革命主義を改め、選挙で民主的に政権を掌握することを志向した。
ヒトラーが収監されている間に、ドイツの内政と経済はかなりの改善を見た。時の首相シュトレーゼマンは、1兆マルクを1マルクとする大幅な通貨切り下げを行い、ハイパーインフレの鎮静化に成功した。また、アメリカの介入により、連合国による賠償規定も見直され、ドイツにとって支払いがしやすくなったとともに、外債によるドイツへの借款も用意されたため、ドイツ経済は立て直しのきっかけを掴むことが出来た。
さらには、ドイツの賠償金支払いが再開されたことで、フランスもルール地方から撤収。また、ロカルノ条約の締結によって、ドイツは国際連盟に加盟することが許され、国際社会に復帰した。
ヒトラーは、この相対的安定期と呼ばれる時期に出所し、ナチ党の議席獲得に奔走するわけだが、その道のりは非常に困難なものとなった。彼の過激な行動理念は、ミュンヘン一揆の時には、ハイパーインフレの動乱と、それに伴う国民の不満が頂点に達していたため大いにもてはやされたが、経済が持ち直してくると、ワイマール共和国打倒を主張し続けているナチの主張は危険思想として毛嫌いされた。
しかし、そのヒトラーにとって、願ってもない状況が訪れる。1929年の世界恐慌である。ドイツは再び深刻な経済危機に見舞われ、工業生産は半分に落ち込み、1930年には失業率15%、失業者数300万人に達し、1932年には、失業者数は30%を超え、550万人に及ぶ失業者が街に溢れた。
再び訪れた困窮。軽減されたとは言え、戦時賠償の支払いも未だ終わっていない。地獄のようなハイパーインフレーションの時代を経て、漸くここから世の中が良くなっていくだろうという期待を持ちつつあったドイツ国民の前向きな気持ちは、今度こそ根元から踏み潰された。この時の人々の絶望の深さは、いかばかりであったか。絶望はやがて憎しみに変わった。
目の前にあるこの窮状はいったい何なのだ?誰のせいでこのように惨めな状態に陥ってしまったのか?ドイツ全土に、そうした人々の怒りと憎しみが渦巻いた。その先には、こうではない世界を、力強いドイツを実現してくれる人物はいつ現れるのかという、熱烈な期待も生まれていた。
これをもって、ヒトラーの時代を迎える準備が整ったといってよい。彼は、人々の訴えに応えることが出来た。人々の不安と憎しみを操ることこそ、彼の身に備わった天武の才能であった。このような経緯を経てドイツは、遂に狂乱の時代へと突入して行ったのである。
<12>

世界恐慌による動乱の追い風に乗ってナチ党は躍進し、1932年の選挙では230議席を獲得し、遂に第一党となった。しかし、この時のドイツの総議席数は584議席で、230議席ではまだ過半数に達していない。しかも、ワイマール憲法において、首相の任命権は大統領にあり、時の大統領ヒンデンブルグは、ヒトラーを“ボヘミアの伍長”や“ペンキ屋”と呼び蔑んでいたので、ヒトラーが簡単に首相の座につくことは出来なかった。
ヒンデンブルグはヒトラー封じ込めのための首相を2度にわたって擁立するが、いずれも短命に終わり、いよいよヒトラーしか選択肢がなくなってしまった。1933年1月30日、ヒンデンブルグはやむなくヒトラーを首相に任命。ヒトラーとナチ党員は歓喜した。
しかし、ヒンデンブルグとドイツ政界では、ヒトラーを首相の座に座らせたのは第一党としてのナチ党の議席数を利用するための便宜的なものであり、ヒトラー以外のナチ党員は2名しか内閣に入れていないこともあり、ヒトラーは政局をコントロールできずに早々に失脚するだろうと楽観視していた。
しかし、軒を借りて母屋を乗っ取る能力にヒトラーがいかに秀でていたかは、彼がナチ党を乗っ取っていった過程で既に証明済みだった。実際、ヒトラーは、それまでを遥かに上回るスケールで、その得意技を演じて見せた。
ヒトラーは、首相就任早々に国会を解散、3月5日の総選挙実施を決定し、議席増加の勝負に出た。その選挙期間の真っただ中の2月27日夜に、何者かにより国会議事堂が放火された。ヒトラーはこれを共産党による犯行だと断定し、ヒンデンブルグに緊急事態を発令させ、共産党の一斉摘発に乗り出すとともに、これは共産党が全国レベルで計画しているクーデターの一環であり、富裕者の資産は剝奪され、官憲に従事する者の妻子は拘留されて人間の盾にされると国民に情宣し、恐怖心を煽った。
ヒトラーは緊急事態宣言に乗じ、報道、表現、集会の自由を停止させた。また、連邦であるドイツの大部分を占めるプロイセンの内相に就任したナチ党ゲーリングの指揮下、ナチ党は警察の内部にも勢力を拡大させて民衆への諜報網が張り巡らされ、密告が奨励された。また、突撃隊は、共産主義者のみならず、あらゆる政治的反抗者やユダヤ人に暴行を加え、強制収容所に送る行為を公然と開始した。
ヒトラーは、選挙資金に国庫を流用して大規模な選挙活動を行い、3月5日の選挙で議席数をさらに伸ばし、クーデターの首謀者であると決めつけた共産党の議席を事実上はく奪。さらには中央党、国家人民党を抱き込んで3分の2の議決権を確保すると、満を持して全権委任法の可決を国会に諮った。
ワイマール憲法では、議会の3分の2の承認があれば、憲法に反する法令の制定が可能だったため、ヒトラーはこれを利用し、自身が国政の全権を掌握する法令の制定を目論んだのである。全権委任法は3月23日にあっけなく成立し、ヒトラーは事実上の独裁者となった。
その後も、ヒトラー政権は7月までに他の政党を強制的に解散させて一党独裁体制を成立させ、さらに8月2日にヒンデンブルグ大統領が死去すると、ナチ党党首、大統領、首相の全ての権限を掌握する総統に就任し、ヒトラーはいよいよ完全な独裁者となったのである。これをもってワイマール共和国は消滅し、ドイツは第三帝国として生まれ変わった。ヒトラーの首相就任から、わずか半年と数日のことであった。
独裁とは、全国民を服従させることである。第三帝国でヒトラーとナチ党独裁の支配下にあったドイツ国民は、以下の4つに分類できるのではないかと自分は思う。
まずその第1は、熱狂的な信奉者たちである。1932年の選挙でのナチ党への投票者が4割弱だったので、瞬間最大でそれぐらいの数がこの集団にいたと思われる。或いはもっと多かったかもしれない。彼らは、ヒトラーの弁舌、思想、人格に心から心酔し、その栄光を信じて疑わなかった。第2の集団は、その熱狂的支持層に付和雷同し、何となくついていくもの。第3は、ヒトラーやナチ党のやり方に違和感、場合によっては嫌悪感を感じているが、疎外や暴力が怖くて黙ってついていくもの。そして第4は、ナチ思想に賛同せず、社会的、さらには物理的に抹殺されていった者たちである。
為政者として、1と4の両脇を抑える手段を確保してさえいれば、真ん中の2と3はなんとでもなる。そして、4の暴力の担い手は、1に属する熱狂的信奉者の精鋭によって組織される。ナチ党でいえば、SSと呼ばれた親衛隊がその中核である。悪名高きゲシュタポも強制収容所も、SSの傘下にあった。
要するに、この熱狂的信奉者の獲得と維持こそが、ヒトラーの独裁の原動力であったといえるだろう。彼はいかにしてそれを手中に収めたのか。熱狂的信奉者を引き付ける手段。その最たるものが、ヒトラーに備わった天武の弁舌の才だった。
ヒトラーの弁舌の才は、首相就任演説に典型的に表れている。ヒトラーは超満員の会場に、密集した何十ものナチ党旗の煽動に導かれ登場した。勇ましいナチの制服を身にまとったヒトラーが会場の壇上に立つと、場内は割れんばかりの歓声で興奮状態に陥った。
会場の興奮と歓声、感極まった男たちの怒号は収まらない。その間、ヒトラーはただ黙って壇上から民衆を睥睨し続ける。数分も経っただろうか。漸く人々は静まり、自分たちの新しいリーダーが何を話そうとするのかに耳を傾けようとする。聴衆の関心が自分に集まったことを確認すると、ヒトラーは、低い声で静かに話し始める。
まず彼は、自らとナチ党が政権に参画したことを厳かに宣言する。そして自分が、何のために今日まで闘ってきたのか、今この立場を得て、国民たちと何を成し遂げようとしているのかを説明したいと語る。会場の空気はヒトラーの周りに徐々に濃縮されていく。
ヒトラーは、ワイマール共和制になってからの14年の恥辱の歴史について振り返る。彼の声は徐々に大きくなり、やがては、両腕での激しいゼスチャーを伴い、興奮のボルテージを上げていく。
ワイマール政府の迷走による政治的混乱と無力なる統治。その結果もたらされたものは何であったか。屈辱的な賠償。国家の荒廃。あらゆる資産価値の喪失。インフレ。そして失業。百万が二百万となり、三百万、四百万・・・遂に七百万に及ぼうとしている。彼が、短く鋭い言葉で叫ぶたびに、怒涛のように会場からの唱和の声があがる。
2時間にわたる演説が最高潮に足したところで、ヒトラーは、この屈辱を脱するためには、ドイツの全国民が、それに立ち向かわんとする確固たる意志を持ち、勤勉と、誇り、そして強さをもって、本来のドイツが持っていた栄光を、自らの手で勝ち取らねばならないのだと締めくくる。この、魂の叫びのような演説の締めくくりをもって、会場の意思が完全に一つになった。
分裂と迷走。確かにそれが、それまでの十数年のドイツの屈辱の原因だった。今ここに改めて、確固たる意志の元にドイツが統合されようとしているのである。会場には割れんばかりの興奮の声と拍手が渦巻き、人々は立ち上がってハイル、ハイルと絶叫した。人々の大興奮の中、会場にはナチ党歌が流され、親衛隊に囲まれたヒトラーが会場から去っていった。
それがヒトラーの恐ろしさである。彼の主張は、人々の感情に訴え、思考力を麻痺させた。彼の言葉には人を酔わせる力があり、彼という一個の人格には、催眠的磁力とでも言うべき魔力が備わっていた。
ヒトラー自身がこう述べている。「自分は時々、自分自身がしゃべっているのではなく、自分の中にある何かがしゃべっているのに気づくときがある。」また、アインシュタインが相対性理論を発表したことに関連してこうも言っている。「人間の感性で理解できても、論理的には説明できないことがある。にも拘わらずそれは真理であり、新しい世界の基礎となるものである。だから論理的につじつまが合わないような考えが浮かんだとしてもがっかりしなくてよいのだ。」
まことに、ヒトラーは、彼個人の意識を超えたなにものかと繋がっていたとしか思いようがない。ヒトラーは、間違いなくカリスマであったし、救世主ですらあったであろう。その導く先が正しかったかどうかは別である。人々の期待を一身に集め、それまでと全く異なる世界を実現したのだから、少なくともその途上において彼は、彼の信奉者たちにとっての救世主であった。
<13>

この時期のドイツ国民、さらには、彼らを導く存在であったヒトラー自身をも動かしていたものとして、背後に「神話」が存在していたとの見方がある。
その説を述べたのは深層心理学者のユングである。ヒトラー的世界が絶頂に達しつつあった1936年に、ユングは「ヴォータン(※Wotan)ほど、ナチズムを説明する因果仮説としてうまく当てはまるものはない。」と言っている。ヴォータンとは、北欧神話に出てくるゲルマンの主神である。以下、ユングの弟子である河合隼雄氏の著書、「中空構造日本の深層」の「偽英雄を生み出した『神話』」の章からから引用したい。
※ ヴォーダン/Wodanともいう。
「ゲルマンの神々はキリスト教によって地下に押し込められ、その上に近代合理主義という舗装を行って、すべて安泰と思われていたとき、二千年近い眠りを破って、ヴォータンは火山の爆発のごとく、全てを突き破って二十世紀の文明国に躍り出てきたのである。」
「ヴォータン(は、北欧神話の主神であり、『嵐と狂奔の神であり、情熱と闘争心を解き放つものであり、さらには優れた魔術師、幻術の使い手』なのである。嵐と狂奔の神としてのヴォータンは、ゲルマン全土にわたって信じられている。嵐の夜にはヴォータンの軍団が山野を駆け抜けていくという伝説に示されている。それは、「怒り狂った軍団」であり、これこそ、ナチス軍団がヨーロッパを駆け巡った姿にぴったりと思われる。ヴォータンはまた美男で雄弁であるとされた。彼が言うことは何でも、それを耳にするものにとっては真実のように思われるという。」
神話とは、論理的に説明できない世界である。ヒトラー自身が言っている。「人間の感性で理解できても、論理的には説明できないことがある。にも拘わらずそれは真理であり、新しい世界の基礎となるものである。」
ヒトラーはまた、ヴォータンそのものについても、自身で言及していたことが、彼が幼馴染に再会し語った内容として残っている。ユングがヴォータンを引き合いに出した2年後の1938年、ナチスドイツがオーストリアを併合し、ヒトラーが故郷に“凱旋”した際のことである。ヒトラー本人の人生における歓喜の絶頂の瞬間といっていい。
ヒトラーは、ウイーンの王宮のバルコニーに立ち、眼下にひしめく民衆を相手にオーストリアの併合を宣言しようとした。その時彼は、一瞬だが、呼吸困難に近い状態に陥り、視界も半ば失ってしまった。その時彼の目に映ったのは、古代ゲルマンの天界ヴァルハラから出てくる軍勢と英雄たち、そしてその背後に輝く光の中に在る主神ヴォータンの姿だったという。
独裁者となったヒトラーは、自身を神の意志を受けた救世主であると認識し、時にそう公言した。事実彼には、人知を超えた何かがあった。
ある時点からのヒトラーには、それまでの彼、すなわち、問題児であった思春期、売れない画家志望だったウイーン時代、変わり者の伝令兵だった第一次世界大戦の頃とは全く違う何かが存在したのである。揺るぎなき意志の力、圧倒的な悪運の強さ、彼の熱狂的信奉者はもちろんのこと、彼を嫌悪するもの、嘲るものまでをもいつの間にか巻き込み、その気にさせ、或いは抹殺して、全てを自らの手中に収めてしまう行動力。いったい何がヒトラーを変えたのか。そこに、第一次世界大戦の終戦時に彼が経験した失明が関係しているとする説がある。
ヒトラーが、伝令兵として従軍していた第一次大戦末期に、ベルギー方面の前線でマスタードガスを浴びて野戦病院に入院したこと、そこでドイツ敗戦の報に触れてパニック状態となり、ヒステリー性と思われる失明状態に陥ったことはすでに触れた。人は、受け入れがたい状況に直面した際に、肉体的には何も問題がないにも関わらず、本人が意識しない精神の働きにより、その部位の機能を停止させてしまうことがあるという。所謂、転換症状である。ヒトラーの場合は視力であった。
青年期までのヒトラーの人生には、輝かしいものは何ひとつなかった。ヒトラーはそれを、自分を取り巻く世界の在り方がおかしいからだと考え、自らを不当な地位に貶めた世界、ハプスブルグ王朝末期の母国オーストリアの在り方を心から憎んだ。
そんなヒトラーにとって、国境のすぐ向こうのドイツ帝国は栄光の存在であった。そこに行けば、よりまっとうな世界の在り方の中で、正当な自分の立ち位置を確保出来るかもしれない。ヒトラーは、バイエルン陸軍に志願して伝令兵となり、一定の戦果を治めた。伍長格以上にはなれず、客観的に見えれば実にささやかな成功だったが、それでも彼にとっては、自らの手で勝ち取った何にも代えがたい大事な拠り所だったのかもしれない。
そのドイツ帝国が、あっけなく敗戦してしまったという。それは同時に、彼がそれまでの人生で唯一見出した居場所である陸軍部隊という足場も失うことを意味した。散々な不遇を経て、漸く手中に収めつつあった希望が、今再び召し上げられ、自分は闇の元へと押し戻されようとしている。あんまりではないか。ヒトラーは、失意のどん底に陥った。彼はこの世の全てがいよいよ嫌になり、その拒絶反応が失明という形で現れたのかもしれない。
当時ヒトラーが収容されていたパーセヴァルクの野戦病院に、エドムント・フォルスターという神経科医がおり、ヒトラーの症状をヒステリー性の失明であると診断した。当時、精神を病んで入院する前線兵が多数いたという。また、ヒステリー性の失明を発症するものも当時は多く、フォルスターも、そうした治療を行ったことが、それまでにも何度かあったようである。
フォルスターは、極めて腕の良い精神科医だったようである。ただ、気性が激しく、支配欲が強い等、どこかヒトラーと似たところがあったのかもしれない。フォルスターは、ヒトラーの目を見えなくさせているのは、彼自身の精神による意識せざる封印にあると診立て、それを解きほぐし、取り除くための治療を行った。
その種の精神治療を行う際には、患者をリラックスさせ、逆にストレスも与え、相反する2つの事象を示して敢えて患者を混乱させる等、様々な手法を使って問題の核心に迫っていくらしい。フォルスターは、ヒトラーが失明の闇から戻ってくる梃(てこ)として、ヒトラーの屈折した自尊心と、彼が座右の銘として掲げる「天は自ら助くる者を助く」という、“意志の力”を大いに活用した。
奇跡でも起こらなければあなたの目は治らないが、奇跡などは、そもそも起こりえないものである。ただ、それは凡人についてであって、選ばれし者の前には自然の摂理までもが頭をたれ、奇跡が現出する。それを成し遂げるのは、他ならぬ本人の意志の力である。見ようとする意志があるかないか。そうではないか?あなたは特別な人間であり、その奇跡を起こす力が備わっているはずではないか。
自分は、そのような治療を受けたことがないし、催眠療法の詳細も知らない。そういうレベルでの推測ではあるが、そうした治療の現場である精神の奥深くは、言語では表現できない概念、もしくは想念の世界なのだろうと想像する。そういう世界で、フォレスターは、暗い闇の中を彷徨うヒトラーの魂に呼びかけた。
フォルスターは、催眠状態に陥ったヒトラーの自尊心を擽り、魂を鼓舞し、世の中に絶望して光をとらえることを止めた目に、再び光を与えようとした。彼がそのような治療をヒトラーに施した動機は、自らの患者の病状を治したいという、極めて当たり前な職業倫理にあったのかもしれないし、或いは、自らの腕前を振るって、このややこしそうな症例を見事解決してみたいという好奇心や功名心のようなものも、少なからずあったかもしれない。
ヒトラーは、その治療の甲斐があって見事に視力を回復した。そして、この時を境に彼は、それまでとは全く違った人格になっていった。
以下は自分の勝手な想像である。
ヒトラーの瞳は光をとらえることを拒否し、彼の意識は、深い心の闇の中へと沈んでいった。そこでは、彼個人がそれまでの人生で感じ続けた恨みや妬み、憤り等の感情が黒々と渦巻いていた。それはあたかも深い森のようで、その森の奥はそのまま、ドイツの民族全体の集団無意識へと繋がっていた。
ドイツ民族の本当の苦しみは、第一次大戦後の巨額の賠償と内政の混乱によってより深刻なものとなるが、第一次世界大戦の末期には既に、経済封鎖による食料難で餓死者が多数出る等の困難に直面し、看過できないレベルに達していた。そこにさらに敗戦という苦しみが加わり、激しい憎悪がぐろぐろととぐろを巻き、大きな塊となって生命を宿し、不気味な蠕動を始めているところであったのかもしれない。恐らくヒトラーは、彼の心の闇のずっと奥で、その何物かと邂逅したのであろう。
そんな暗く深い心の闇を彷徨っていたヒトラーのことを、誰かが遠くから呼ぶ声が聞こえた。彼はそれを神の声と認識したが、果たしてそれはフォルスターであった。フォルスターは、意識の底の森を彷徨うヒトラーに、現実世界に戻って来いと呼びかけた。君にはその力があるのだ。自らの意思を信ぜよ。君は選ばれた存在なのだ。
ヒトラーは、暗い森を抜け、意識の階段を光の方へと登って行った。その後ろに、彼が闇の中で出会ったあのモノが付いてきていることを、果たして彼は知っていたか。或いはヒトラーは、深い暗闇の世界で、その存在と何らかの契約を交わし、承知の上でその存在を地上に連れ出したのかもしれない。いずれにせよそれは、治療医フォルスターの全くの想定外のことであったろう。
再び光の世界に戻ってきたヒトラーは、全くの別人になっていた。彼は、政治家になることを決意した。ヒトラーの青い目は不気味な光を宿し、その目で見つめられると、誰しも射すくめられたようになったという。彼の弁舌には、言葉を超えた何か特別な力が宿り、人々を熱狂させ、その思考力を麻痺させた。政権獲得までの幾度もの政治的駆け引きも神がかった勝負強さで切り抜け、何度となく目論まれた暗殺計画ですら、動物的感で都度難を逃れ、ナチスという狂気の集団を率い、全欧州を戦争と圧政と殺戮のどん底に陥れた。
以上、ヒトラーがヒステリー性失明に陥り、それを治すための催眠治療が彼の人格を変えたというのは、あくまで一つの仮説であり、何が真実であったかは今となってはわからない。わかっている事実は、ヒトラーが、独裁者となって早々に、躍起になって当時の治療記録を抹消したことと、ヒトラーに催眠治療を施したフォルスターが、逃亡先のパリで追い詰められるようで自殺を遂げたことだけである。
自分がここで言いたいのは催眠治療の云々ではない。独裁者であった頃のヒトラーには、人知を超えた何かがあった。それは、多くの人が感じているところであろう。自分の関心は、ヒトラーに悪魔のような力を与えたのは、人々の心に渦巻く怒りや憎しみ等の負の情念ではなかったか、という点にある。
様々な経済的、精神的困窮の中で、世界中の人々の間で限界まで蟠っていたストレスのような黒い何物か。それが、世界で最も濃縮された場所がたまたま当時のドイツであり、それが地上に噴き出るための便宜的な噴火口がヒトラーという一個人だった。そう捉えることは出来ないだろうか。
ヒトラー個人の人道的責任についてはもはや論ずるべくもない。その狂気の執行に図らずも加担してしまったドイツ国民の責任についても、彼ら自身が最も深刻に、大いなる苦悩とともに受け止めているところであろうし、自分がそれについて何かを述べる立場にはない。
ヒトラーという狂気について自分は思う。あのように濃縮された負の情念の湧出を成さしめた責任、そして、そこまでの人々の心の歪(ひずみ)を溜めさせた責任という観点で、世界の人々全てが、その蛮行の一端を担っていたと言えるのではないかと。そして、あの時代に限らず、我々人類は常に、そのような状況を生み出してはならないという責任を、共同して負っているのではないか。そう思うのである。
その認識を疎かにし、怒りや憎しみの負の情念に流されてしまえば、あのような悲劇が、また世界のどこかで再現されるであろう。それが、独裁者の出現という形を取るかどうかはわからない。しかしそれが、国家間の対立を全面的な戦争に繋げる大きな負のエネルギー源となってしまうことは間違いない。自分が、独ソ戦について書いているのは、そうしないためにはどうしたらよいかを考えたいと思っているからである。
<14>

1945年4月20日、ヒトラーは、56歳の誕生日を、ベルリン中心地に設けられた総統地下壕で迎えた。その地下壕があるベルリン中心部は、既にソ連赤軍によって包囲されている。
ヒトラーという、青年期は売れない画家であり、第一次世界大戦中は奇人とも呼ぶべき性癖のしがない伝令伍長でしかなかった男は、政治家として成功し、1933年の全権委任法成立によって独裁者としての地位を獲得して以降、魔神の如き働きで、第一次大戦後の恥辱と貧困のどん底にあったドイツという国家とその民族を、再び一流国の地位に返り咲かることに成功した。その成果は、政治、外交だけでなく、軍事、経済や科学技術の多岐に及ぶ。
軍事においては、機動力の高い戦車群とそれを空から援護する急降下爆撃機を組み合わせた“電撃戦”という戦術を生み出し、これを駆使してヨーロッパの大部分を制圧した。また、ロンドン空爆で使用した無人飛行機型の長距離爆弾V1の後継として、成層圏を経由して敵国に攻撃を加えるという、それまでに全く存在しなかった種類の兵器V2ロケットを開発した。後の米ソの宇宙開発戦争、そして、弾道ミサイル配備による冷戦は、ナチスが開発したこの技術を米ソ両国が持ち去ったことに端を発している。
経済面においても、ヒトラーは失業者を劇的に減らし、また、一般庶民でも休暇には自家用車に乗って保養地にバカンスに出かけられる社会の実現を提唱し、具体的な政策を掲げた。戦後のモータリゼーションより遥か前の1930年代の話しである。このビジョンは、しっかりと実政策に落とし込まれ、その結果普及したのが、現代でもドイツが世界に誇る高速道路網アウトバーンであり、また、庶民の給与で買えて家族みんなで乗れるとのコンセプトで彼がポルシェ博士に命じ設計させた”国民車”、ドイツ語でいう“Volkswagen”のビートル(ドイツ名ケーファー)であった。ビートルは、後に世界中に輸出され、現在に至るまで史上最多の製造台数を記録する車となっている。もっとも、ヒトラーの時代のビートルは軍用車としてのみ使用され、民間用の車として量産されたのはナチス敗戦後の“西ドイツ”においてであったが。
要するに、ヒトラーがドイツ国民に輝かしい栄光と繁栄をもたらしたことは、紛れもない事実なのである。
ヒトラーは、それまでの歴史上、地球上のどこにも存在しなかった特異なる世界を作り出したと言って良い。ヒトラーという一個人が、国家としてのドイツと、全ドイツ国民に対する絶対的な支配権を有する世界である。多くのドイツ国民は、そのナチ的世界を熱狂的に支持し、その世界を発展させるための執行者となって行動して、繁栄を享受した。
しかし、ヒトラーのナチ的新世界は、大躍進と絶頂の時代において既に、繁栄の光芒の裏側の漆黒の闇も抱えていた。ドイツ国民は、そうした闇の部分に対し、繁栄のコストとしてそれを容認するか、違和感があっても口をつぐむかしかなかった。その世界の在り方に異を唱えれば、ゲシュタポに捕らえられて強制収容所に送られるか、即刻処刑されるか、いずれにせよ、栄光あるドイツ第三帝国の構成員という地位、人間としての尊厳、場合によっては生命そのものを剝奪される恐れがあったからである。
不思議なのは、社会の構造が単純であった古代ならともかく、政治、軍事、経済ともに高度に組織化された20世紀の近代国家というものを、たった一人の独裁者が、どのようなマジックを使って、あれほどまでに機動的に運営していくことが出来たのかという点である。
ヒトラーが独裁者となった後も、日々の行政の執行は既存の官庁、官僚が担い、軍事は国防軍によって、産業と経済は実業界によって運営されていた。その機能を損ねず、かつ、ヒトラー個人がそれらの全てを束ね、意のままに操るために彼が発明した偉大なるシステムが、“指導者原理/Führerprinzip”である。
ヒトラーが、彼が掌握する絶対的かつ超法規的な権力の一部を、その腹心に分け与える。腹心は、神権とも言うべきヒトラーの超法規的な権限の分与の見返りとして、彼に対する絶対的な服従を誓わなければならない。あるものは怜悧なる打算の上でこの取り引きに応じ、またある者は、ヒトラーの思想とその存在そのものに、心から心酔してこの枠組みの執行者となった。
この、絶対的権力のねずみ講とも言うべきシステムが、ナチスドイツの統率原理の根幹である。その全体を束ねうるのは、ヒトラー個人ただ一人である。
いや、確かにヒトラーはその中心点にいたが、この仕組み、この巨大な渦そのものが、一個の独立した生命体と言ってもよいかもしれない。ヒトラー本人ですら、この生命体の便宜的中心点に過ぎず、ましてや、ナチ党や親衛隊などは、この生命体の意思を実社会ににて具現化させるためだけの、手首から先程度の存在だったのかもしれない。
この生命体が、積年に渡るドイツ国民の苦しみ、恨みによってため込まれた膨大な負の情念のエネルギーを糧としたことで、爆発的な活力となってドイツを復興へ導き、同時に、悪鬼の如き破壊力を体現して、全ヨーロッパを席巻した。善良なるドイツ国民のみならず、英仏の近隣列強の外交と軍事をもってしても、その勢いを止めることは出来なかった。
ただし、この魔物にも弱点はある。一つの極点に力を吸い集める不可逆的な力学構造にあるため、その構造の一部に何らかの矛盾や歪みが生じても、それを自ら開放・排出し是正するという、生命維持のためのバランスのメカニズムを持たない。矛盾や歪みを含む全てを権力の中枢へと吸い上げ続けるため、やがてこの生命体そのものが、ブラックホールの如き巨大な矛盾の渦と化してしまう。それがおかしいと多くの人が気づいても、その渦自体が世界の在り方そのものであるため、誰も異を唱えることが出来ない。ただただ、その渦に巻き込まれ、流されていくだけである。
ドイツという国家が、どのような顛末によってヒトラーという狂気の男を独裁者に推して開戦に踏み切ったか、その後のドイツが、英仏米、そしてソ連とどのような戦局を展開してきたかについては、これまでに書いてきた通りである。ヒトラーと第三帝国、そしてドイツ国民は、一旦は頂点を極めるが、やがて坂を転げ落ちるように形勢を悪化させ、遂に、ソ連赤軍により帝都ベルリンを包囲されるに至った。
それが、1945年4月末のベルリンの情景である。天才ヒトラーによって生み出された狂気の世界が、終わりを告げようとしている。その地獄の断末魔について、書かねばならない。
2020年7月~2021年5月